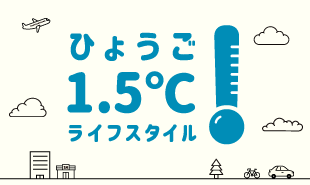法第3条、第4条、第5条、第14条の調査の結果、土壌汚染状況調査の汚染状態が指定基準に適合しない場合、知事により汚染区域として指定されます。また、人への健康被害が生ずるおそれの有無により、指定される区域(有:要措置区域、無:形質変更時要届出区域)がわかれます。
形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更しようとする場合には、事前に届出が必要です(法第12条)。
概要
知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
なお、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなった場合には、指定が解除されます。
区域の指定・解除は、知事が公示することによってその効力が生ずることとされています。
(1) 要措置区域(法第6条)
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合せず、有害物質の摂取経路がある区域です。
健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染除去等計画を作成し、これに基づき汚染の除去等の措置を行う必要があります(法第7条)。土地の形質変更は原則認められません(法第9条)。
措置の実施等により、土壌汚染の摂取経路の遮断が行われた場合、形質変更時要届出区域へと切り替えられることとなります。
(2) 形質変更時要届出区域(法第11条)
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準に適合していませんが、土壌汚染の摂取経路がない区域です。
健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。しかし、土地の形質変更時に知事に計画の届出が必要です(法第12条)。
兵庫県の所管する地域(土壌汚染対策法政令市の所管する地域を除く。)での区域指定状況
区域の分類
区域の指定は、要措置区域と形質変更時要届出区域の大きく2つに分かれます。また、形質変更時要届出区域は要件により、さらに4つに区分されます。
自然由来特例区域又は埋立地特例区域に指定されると土地の形質の変更にあたり、基準不適合土壌が当該区域の帯水層に接しても差し支えなくなります。また、埋立地管理区域に指定されると、地下水位の管理又は地下水質の監視を行いながら施工すれば、基準不適合土壌が当該区域の帯水層に接しても差し支えなくなります。
横スクロール
| 区域の分類 | 定 義 | |
|---|---|---|
| 要措置区域 | 人の健康被害に係る被害を防止するために汚染の除去等の措置を講じることが必要な区域 | |
| 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 |
一般管理区域 | 人為的な特定有害物質により汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときに届出をしなければならない区域 |
| 埋立地 管理区域 |
① 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域内にある土地であって公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成されたもの ② ①に掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり地下水の飲用利用等に係る要件(規則第30号各号)に該当しないと認められるものであり、かつ、公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成されたもの |
|
| 自然由来 特例区域 |
形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(シアン化合物を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。) | |
| 埋立地 特例区域 |
昭和52年3月15日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。) | |
様式
様式第15 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(wordファイル)