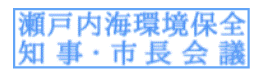1 瀬戸内海の移り変わり
(1) 高度経済成長がもたらした弊害(1960~1970年代)
瀬戸内海は古くから比類のない美しさを誇る景勝地として、また豊かな漁場として私たちの暮らしに豊かさをもたらして
きました。しかし、高度経済成長期に入り、都市化、工業化が進み、工場や家庭からの排水等により海域の水質汚濁(富栄養化)が急速に進行しました。
その結果、プランクトンが大量に発生し、赤潮などにより、漁業・養殖業が大きな被害を受け、瀬戸内海は「瀕死の海」
といわれました。
(2) きれいな海を目指した取組(1970~1990年代)
兵庫県をはじめとした沿岸自治体は、法整備を国に働きかけ、瀬戸内海環境保全特別措置法の制定が実現し、化学的酸素要求量(COD)の流入負荷削減などの環境保全対策を進めました。また、工場等には排水処理施設が導入され、下水道も普及しました。この結果、1980年代以降、兵庫県沿岸の瀬戸内海の水質は大きく改善し、赤潮発生件数も減少しました。
(3) 新たな課題 ~漁獲量の減少と魚介類の異変~ (1990~2010年代)
環境保全対策等により、水質が大きく改善された一方で、1990年代後半から兵庫県沿岸の瀬戸内海の漁獲量が減少しています。また、以前より痩せた魚が多くなり、養殖ノリの色落ちが頻発するなど、瀬戸内海の「豊かさ」が失われてきました。
この要因の一つとして、食物連鎖の底辺を支える植物プランクトンの栄養となる窒素やりんの不足が指摘されています。
(4) 豊かで美しい里海の再生に向けて(2010年代~)
人手が加わることで生物生産性と多様性が高くなった沿岸域、いわゆる「里海」として瀬戸内海を再生するため、兵庫
県をはじめ沿岸自治体は、国に法整備を求めました。その結果、2015年に瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され、豊かな海を目指すという基本理念が新たに設けられました。
2 豊かな海の再生に向けた取組
① 海域における栄養塩類の「望ましい濃度」の設定
2019年に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、全国初の取組として、海域における栄養塩類の望ましい濃度を設定しました。
(下限値 窒素:0.2mg/L、りん:0.02mg/L)
改正した「環境の保全と創造に関する条例」関係資料(PDF)(550KB)
望ましい栄養塩濃度を定めた告示(PDF)(45KB)
② 兵庫県栄養塩類管理計画の策定
2021年6月には、瀬戸内海環境保全特別措置法が改正され、特定の海域への栄養塩類供給が可能となりました。兵庫県は、2022年10月に他府県に先駆けて同法に基づく「栄養塩類管理計画」を策定し、栄養塩類、特に全窒素の供給量増を目指しています。
③瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画
2023年11月には、SDGsの達成を目指すとともに、「豊かで美しいひょうごの里海」の実現に向けて、「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画」を策定しました。
④豊かで美しい里海の再生を目指して(動画)
豊かで美しい里海の再生を目指した取組について、より多くの方にご理解いただくため、動画を作成しました。
ナレーションとイラストはさかなのおにいさん かわちゃん(川田⼀輝さん)です。
3 瀬戸内海全体の環境保全について
瀬戸内海環境保全知事・市長会議
瀕死の海と呼ばれた瀬戸内海の水質の改善をはじめとする環境の保全を推進するために積極的な広域行政を進めようと、兵庫、広島、香川の3県の知事の提唱により、昭和46年7月14日、神戸において、関係11府県知事及び3政令指定市長により、瀬戸内海環境保全知事・市長会議が開催されました。
この会議で、「瀬戸内海環境保全憲章」を採択し、憲章の精神に則って瀬戸内海の環境保全に努力していくため、この会議を組織化し、以後、広域的な相互協力によって瀬戸内海の環境保全を図るとともに人間性豊かな生活ゾーンを実現することを目的とし、瀬戸内海の環境保全及び快適な生活環境創造のための基本施策の推進、国に対する建議及び要望活動等を行っています。