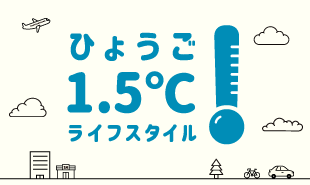第1節 時代の潮流
第1 都市・生活型公害への変化
本格的な成熟社会を迎えた今日、中央集権・一極集中による画一性と効率性を優先する社会システムから、地方分権・多極分散による多様性と個性を優先する生活者の視点に立った新しい社会システムヘの転換が進んでいる。このような時代の変化の中、国内においては、工業地帯での産業公害問題が改善する一方、都市全体からの生活排水や自動車の排出ガスなど、地域に広く分散する汚染源による環境負荷が都市・生活型公害として浮上している。
第2 地球環境問題の深刻化
二酸化炭素(炭酸ガス)等温室効果ガス濃度の上昇による地球の温暖化、フロンなどによるオゾン層の破壊や酸性雨など、地球規模での環境問題が深刻な様相を帯び、世界各国において環境問題への取組が進められている。2005年2月には「気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書」が発効し、今後、より一層の温室効果ガスの排出抑制が求められている。
第3 循環型社会への移行
社会の成熟とともに、人々の意識には、物の豊かさよりも心の豊かさを重視する傾向が強まり、大量生産・大量消費・大量廃棄を生み出す社会のあり方への疑問が広がるとともに、地球温暖化防止をはじめとする環境保全のためには、社会経済システムと一人ひとりのライフスタイルの変革が必要であるという考え方が強まっている。
第4 環境リスクの顕在化
環境に影響を及ぼすおそれのある多数の化学物質が、恒常的に環境中に排出されていることによる人の健康や生態系への影響、ダイオキシンなど微量ではあるが長期的な暴露によって人の健康が脅かされるなどの環境リスクの高まりについて懸念が生じている。そのような懸念を背景として、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法平成11年法律第86号)などに示されるように、人々が環境情報を知ることができるということが重視され始めた。
第5 生物多様性の危機
人間の活動に伴う環境変化の影響により地球上の生物の生息環境の健全性が損なわれ、多くの生物種(生物多様性)や生態系が存在の危機に直面しており、「生物の多様性に関する条約」が1993年に発効するなど野生生物種や生態系を保全するための国際的な取組が展開されている。国内的にも「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)や「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)が制定されるなど取組が進んでいるところである。
第6 環境効率性の重視
経済面においても、環境負荷を低減させながら経済性を向上させる「環境効率」という考え方が世界的に重視され始めた。また、事業者の責任についても「特定家庭用機器再商品化法」(平成10年法律第97号)・「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年法律第87号)の制定に見られるように、「拡大生産者責任」といった新たな考え方が示されるとともに、産業廃棄物等の不適正な処理についても、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」(平成15年条例第23号)を制定する等、取組を進めつつあるところである。
第7 持続可能な社会の形成に向けた取組の活発化
環境省において、「環境と経済の好循環ビジョン」が発表されるなど、環境を良くすることが経済を発展させ、経済が活性化することによって環境も良くなるという環境と経済が一体となって向上する社会の実現が求められている。 このように、持続可能な社会の形成に向けて、個人、民間団体、企業、行政の取組が広い範囲で活発化し、とりわけ、環境と社会と経済の面で、企業の社会的責任がより強く認識されてきているところである。