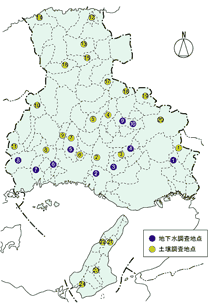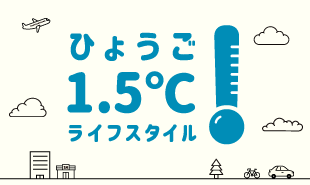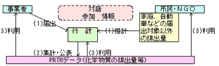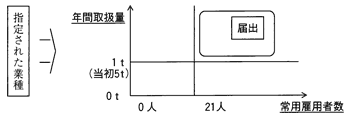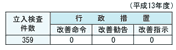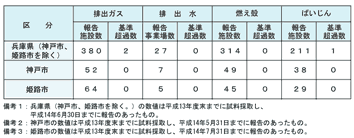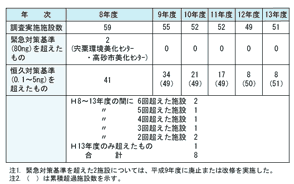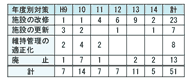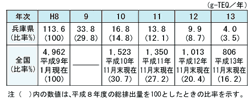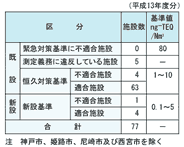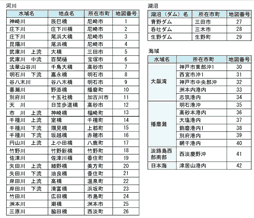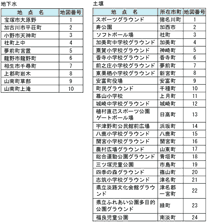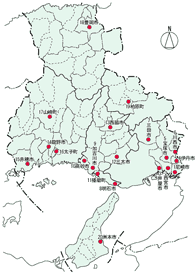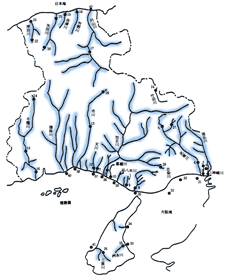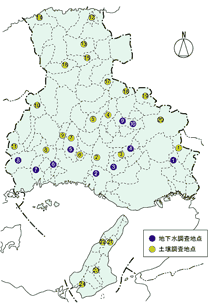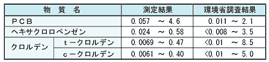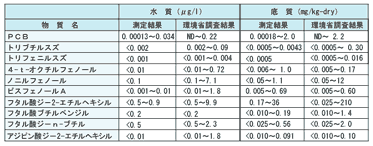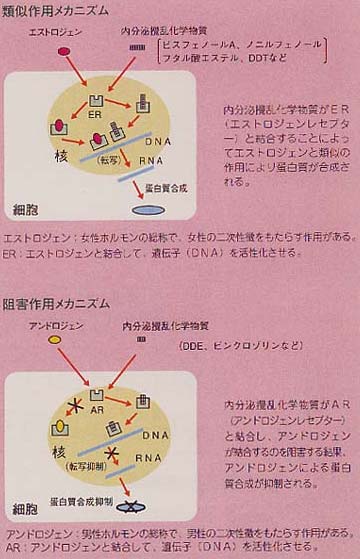第2 ダイオキシン類削減対策
▼コラム ダイオキシン類とは
▼コラム ナノグラム(ng)、ピコグラム(pg)ってどれくらいの量?
▼コラム ダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)
1 発生源対策
ダイオキシン類は、非意図的に生成する化学物質であり、その発生源は有機塩素系化合物の生産過程や廃棄物の焼却過程など多岐にわたっている。また、毒性が強く、その環境汚染が大きな社会問題となっている。
このため、県では、平成9年5月30日に設置した「ダイオキシン類対策検討委員会」の指導・助言のもと、平成9年12月に「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」を策定し、総合的、計画的なダイオキシン類対策を講じている。
また、平成11年7月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、平成12年1月に施行された。この中でダイオキシン類に係る大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・廃棄物処理に関わる基準、規制及び措置等が定められた。
これに基づき、特定施設に係る届出の受理、立入検査により排出基準適合状況等の審査及び指導を行うとともに、工場の調査やダイオキシン類による環境の汚染状況の常時監視を行っている。
(1)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策
ダイオキシン類対策特別措置法の適用を受けている工場等について、特定施設に関する届出の審査及び燃え殻・ばいじんの処理方法の確認を行っている。
平成13年度は延べ359事業所に対して立入検査を行っている(第2-1-38表)。
第2-1-38表 立入検査の状況
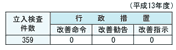
また、ダイオキシン類に関する最新情報の提供等の普及啓発を図っている。
なお、平成14年3月31日現在、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業所数は、大気基準適用施設を設置するものが493(そのうち、同法で権限が委任されている神戸市、姫路市内のものは105)、水質基準対象施設を設置するものが134(そのうち、神戸市、姫路市内のものは30)である。
また、同法に基づき排出ガス、排出水、燃え殻・ばいじんの自主測定及び報告義務が事業者に課せられている。
最近の自主測定状況は、第2-1-39表のとおりである。
第2-1-39表 自主測定結果報告状況及び排出基準の適合状況
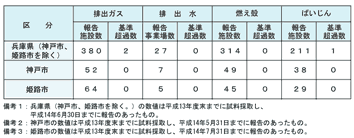
(2)ごみ焼却施設における発生源対策
市町等の設置するごみ焼却施設については、平成10年4月に「兵庫県ごみ処理施設整備基本方針」を策定し、ごみの減量・リサイクルの推進及びごみ焼却施設から発生するダイオキシン類の削減等を図るための基本的な考え方を示した。
同基本方針の中て示されている主な内容は次のとおりである。
・新設されるごみ焼却施設については、原則としてl00t/日以上の規模を持つ全連続炉とし、ダイオキシン対策等の環境保全に係る最良技術を導入した施設とすること。
・発電等エネルギーの有効利用の観点から、可能な限り300t/日以上の規模が確保されるよう、施設整備を進めること。
・離島、過疎地等にあっては、100t/日未満の施設整備も行えるものとするが、施設は連続運転を原則とすること。
この方針に基づき、単独での施設整備が困難な市町等にあっては、複数市町の連携によりごみ処理の広域化を図り、同方針に合致した施設整備を行なうこととなっている。
ダイオキシン類による環境汚染が社会問題化していることから、本県では、「ダイオキシン類対策検討委員会」の指導・助言のもと、平成9年12月に「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」を策定し、これに基づき、全国に先駆けて総合的、計画的にダイオキシン類発生源対策を推進している。
ア 排ガス中のダイオキシン類測定結果
平成8年度から平成13年度までに市町等が実施した測定結果は、第2-1-40表のとおりであり、平成13年度までに恒久対策基準を超えた施設は51施設となっている。
第2-1-40表 ごみ焼却施設のダイオキシン類測定結果
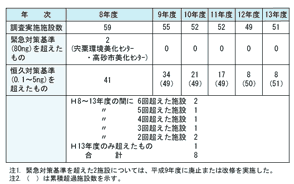
イ 施設の改修状況
県では、国のガイドラインに基づき、法令の規制値より厳しい恒久対策基準(新設基準並)の遵守を指導しており、市町等では、基準を超えた51施設について、法令の適用期限である平成14年12月1日までに恒久対策基準に適合させるよう、施設の改修・更新等の対策を実施している。(第2-1-41表)
第2-1-41表 恒久対策基準を超えた施設の対策
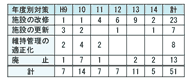
ウ ダイオキシン類の総排出量
平成13年度のダイオキシン類の総排出量は、年間4.0g-TEQで、測定開始の平成8年度と比べて96%削減されており、恒久対策基準をもとに推計した目標値(平成14年度:年間7.6g-TEQ)を前倒しで達成した。(第2-1-42表)
第2-1-42表 ダイオキシン類の年間総排出量
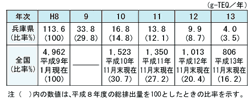
(3)ばく露防止対策(ダイオキシン類による 労働者への健康影響等の防止)
廃棄物焼却施設からのダイオキシン類による労働者への健康影響等を防止するため厚生労働省から「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月)が示されたところであり、県では、市町及び関係事業者等への周知・徹底を行っている。
また、解体時のばく露防止対策により、解体撤去費が高額となっていることから、国に対し補助制度の拡充について要望している。
(4)産業廃棄物焼却施設対策
現在、県下で稼働中の産業廃棄物焼却施設からの排ガスに係るダイオキシン類濃度の測定結果は第2-1-43表のとおりである。
既設については、平成9年12月1日から適用されている排出基準(緊急対策基準)80ng-TEQ/Nm3を超える施設はなかった。一方、測定義務に違反している施設が5施設、平成14年12月1日以降、遵守すべき排出基準(恒久対策基準)を超えている施設が4施設あり、これらについては、測定結果報告書の提出もしくは期限までに基準に適合するよう強力に指導している。
新設では、排出基準を超えている施設が1施設あり、これに対し、改善計画書の提出を求めたうえ、廃棄物分別、温度管理、運転管理の徹底等改善を指導している。
第2-1-43表 ダイオキシン類濃度測定結果
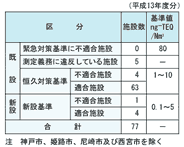
2 環境調査
全県的にダイオキシン類の環境濃度を継続して監視するため、平成13年度においては、大気、水質、底質、地下水、土壌で調査を行った。
(1)大気(資料編第8-1表)
20地点で年4回調査した結果、地点別年平均値で見ると、その濃度範囲は0.039~0.39(全平均値0.11pg-TEQ/m3)で、ダイオキシン類に係る大気環境基準(年平均0.6pg-TEQ/3)をすべての地点で満たしている。
(2)水質(資料編第8-2表)
河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.066~0.87pg-TEQ/l、湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は0.067~0.082pg-TEQ/、及び海域では13地点で調査した結果、濃度範囲は0.065~0.11pg-TEQ/lであり、すべての地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/lを満たしている。
(3)底質
河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.066~130pg-TEQ/g、湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は3.4~16pg-TEQ/g、及び海域では13地点で調査した結果、濃度範囲は0.19~29pg-TEQ/gであり、すべての地点で、ダイオキシン類に係る底質環境基準(ただし、平成14年9月1日から適用:150pg-TEQ/g)を満たしている。
(4)地下水
10地点で調査した結果、濃度範囲は0.039~0.050pg-TEQ/l、すべての地点で、ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/lを満たしている。
(5)土壌
24地点で調査した結果、濃度範囲は0.0030~1.7pg-TEQ/gで、すべての地点で、ダイオキシン類に係る土壌環境基準(1,000pg-TEQ/g)を満たしている。
第2-1-44表 調査地点(大気)

第2-1-45表 調査地点(水質・底質)
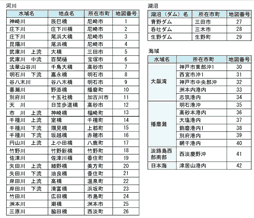
第2-1-46表 調査地点(地下水、土壌)
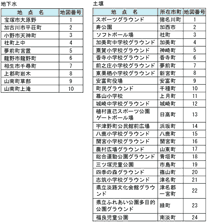
第2-1-63図 ダイオキシン類調査地点図(大気)
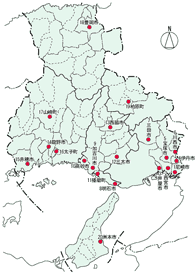
第2-1-64図 ダイオキシン類調査地点図(水質・底質)
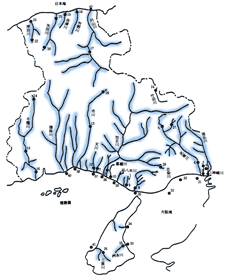
第2-1-65図 ダイオキシン類調査地点図(地下水・土壌)