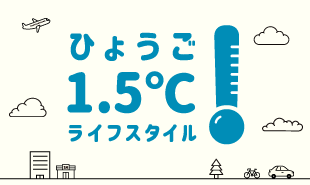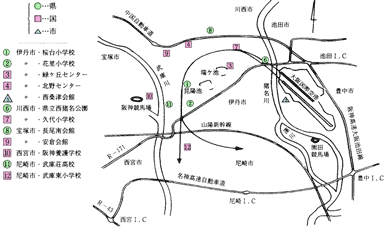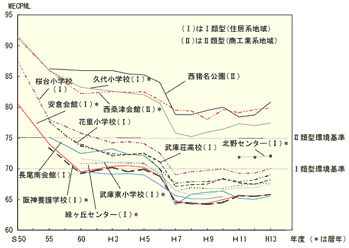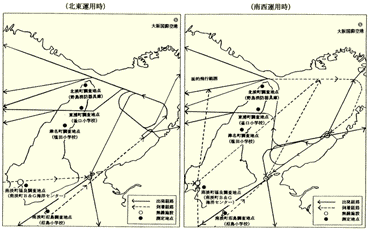第2 関西国際空港
(1)概要
平成6年9月に開港した関西国際空港は、大阪湾南東部の泉州沖にある。平成13年の発着回数は、121,441回(1日平均333回)である。
関西国際空港に発着する航空機の航路の一部は、淡路島の上空を通過している。(第2-1-22図)
第2-1-22図 大阪国際空港周辺におけるWECPNLの推移
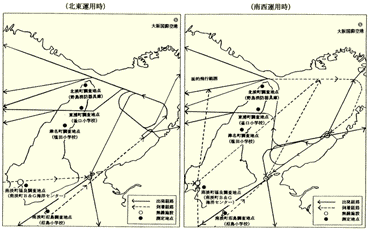
(2)航空機騒音の状況
県が淡路島で行った航空機騒昔調査結果は資料編第4-23表のとおりである。航空機騒音の環境基準の70WECPNL(地域類型・)と比較して15WECPNL以上低くなっている。
(3)航空機公害対策
大阪国際空港の騒音対策は、第2-1-23図のとおり、発生源対策、空港構造の改良及び空港周辺対策に大別される。
1 発生源対策
(1)低騒音機材の導入
昭和52年より航空機の騒音基準に適合した低騒音大型機が順次導入され、現在では、B-727型及びDC-8型の高騒音機は定期路線から退役し、すべてが低騒音機材の運航となっている。
さらに、大阪国際空港では、関西国際空港開港後、騒音基準が強化された新基準に適合した航空機のみの運航となっている。
(2)発着規制
定期便ジェット機の発着回数は、昭和52年10月から年末・年始及び盆の時期を除き、1日あたり200便内で運航されている。昭和63年11月よりYS-11型機の老朽化に対応するため、暫定措置として代替ジェット機発着回数枠が2回にわたり設定され、平成5年には代替ジェット機が100便で運航されていたが、関西国際空港の開港により、代替ジェット機枠は撤廃された。
関西国際空港開港後、定期便のYS-11型機は減少したが、同型機の低騒音ジェット機への代替をさらに進めるため、運輸省は、地元の意向を受け、平成10年3月、定期便ジェット機1日200便の枠外で、YS-11型機の代替等を含み1日50便程度の低騒音ジェット機を導入する計画を示し、平成10年7月から順次運航されている。
さらに、平成14年4月には、プロペラ枠を使用してリージョナルジェット機(小型ジェット機)が運航されている。
また、発着時間規制を行っており、発着は緊急時などを除き午前7時から午後10時までに限られており、さらに、午後9時以降は定期便の設定は行わないこととしている。
(3)運航方法の改善
騒音軽減運航方法として、離陸時の急上昇方式、着陸時のディレイドフラップ進入方式、優先飛行経路の指定なとが採用され、空港周辺への騒音低減が図られている。
風向きなどにより通常(大阪市から川西市方向への発着)と逆方向の発着(いわゆる「逆発着」という。平成13年全発着回数の2.5%)を行うことがある。その場合、視認進入を行うことから、民家防音工事等の対策を実施している区域外に騒音の高い地域が生じている。このため、運輸省は、新AGL(進入路指示灯)を平成11年2月から暫定運用し、飛行コースの改善に努め、このような区域外への騒音影響の低減を進めている。
2 空港周辺対策
ジェット機の就航に伴う航空機騒音問題の発生に対処するため、昭和42年に「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(以下「航空機騒音防止法」という)が制定されたが、航空輸送需要の急激な増大を背景に騒音問題が深刻化したため、昭和49年に「航空機騒音防止法」の改正が行われ、空港周辺地域におけるこれまでの学校、病院などの公共施設に対する防音工事の補助、移転補償などの対策に加え、個人の住宅に対する防音工事の助成、緩衝緑地の造成、空港周辺整備計画の策定とこれを実現するための空港周辺整備機構の設立などの制度が導入され、対策は大幅に拡充されることとなった。
(1)大阪国際空港周辺整備計画
「大阪国際空港周辺整備計画」は、昭和49年に兵庫県知事及び大阪府知事により策定されており、この計画を基礎としつつ、国、地元地方公共団体などは、昭和52年以来周辺地域における望ましい土地利用の方向付け及び特に緊急に整備を要する騒音等激甚地区の地区整備計画の検討を進めてきた。
また、同地域においては、移転補償の進ちょくに伴い、移転跡地が市街地に散在することとなる一方で新たな建物が同地域に立地するなど周辺整備を進めるうえで深刻な問題が生じてきたことから、騒音対策事業のみならず多くの都市整備事業の要請が生じてきた。昭和56年には、このような認識に基づいて、「大阪国際空港周辺の騒音等激甚地区における地区整備の基本的な方向(大綱)」が示された。
一方、低騒音の航空機材の導入などによる発生源対策の進展から、昭和62年1月5日に騒音指定区域(第2種及び第3種区域)の改定が告示され(平成元年3月31目施行)、これにより、第2種区域外に存することとなった移転跡地の有効活用が可能となった。
これらの新たな状況のもと、昭和63年度に伊丹市域及び川西市域地区整備計画案を国、市などと共同でとりまとめ、地元意向を聴きながら、個別事業の実施を進めている。
さらに、平成4年度から、川西市内の小規模な移転跡地が蚕食状に在する地区について、生活環境の改善や地域の活性化を図る地区整備の検討を国、市等とともに行っている。
(2)空港周辺整備機構の設置
空港周辺地域における航空機の騒音による障害の防止及び軽減を図り、生活環境の改善に資するため、国、兵庫県及び大阪府の共同出資により、昭和49年4月に大阪国際空港周辺整備機構が設立された。
その後、昭和60年9月に福岡空港周辺整備機構と統合され、新たに空港周辺整備機構が設立された。
空港周辺整備機構は、再開発整備事業、代替地造成事業、共同住宅建設事業をはじめ、移転補償、緑地造成事業並びに民家防音事業を行っている。
平成15年度には、独立行政法人へと移行することとなるが、共同住宅建設事業を除く各事業については、引き続き実施していく予定である。
(3)住居等移転対策および営業者対策
騒音指定区域の第2種区域内における国の移転補償事業を促進するため、住居等を移転する者が移転資金を金融機関から借り入れた場合に県が移転者に対して利子補給を行っている。
また、移転補償事業の進捗により、顧客の減少など営業環境が変化し、経営に支障が生じている小売業又はサービス業を営む小規模企業者に対し、県が経営の安定に必要な資金のあっせん融資、融資に伴う信用保証料の助成及び利子補給を行っている。
(4)周辺環境基盤施設整備事業
騒音指定区域の第2種区域内において、住環境の改善などを目的とし、地方公共団体が国土交通省の補助を受け、移転跡地の利用などにより、公園、緑道、細街路及び防火水槽などの整備を周辺環境基盤施設整備事業として行っている。
(5)県立西猪名公園の設置
空港周辺における環境整備の一環として、緑地の確保と当該地域の生活環境を向上させるため、移転跡地を活用して県立西猪名公園を設置した。
所 在 地:伊丹市北伊丹8丁目及び川西市久代6丁目
面 積:6.0ha
開園年月目:昭和57年4月8目
施 設:テニスコート、球技場、ウォーターランド等
(6)大阪国際空港周辺緑地
空港と周辺地域との間に緩衝緑地を確保し、空港と周辺地域との調和を図り生活環境を改善するとともに、地域の憩いの場として積極的な利用を図るために大阪国際空港周辺緑地整備事業を実施している。
所 在 地:伊丹市森本及び岩屋地区における空港に隣接するおおむね第3種区域
面 積:約8.6ha
都市計画緑地
事業承認・認可:平成5年9月6目(建設省告示第1801号)
施 行 者:国土交通大臣、兵庫県及び伊丹市