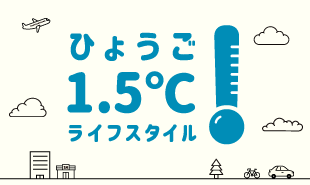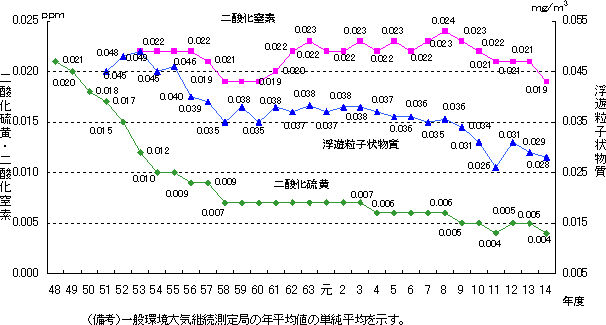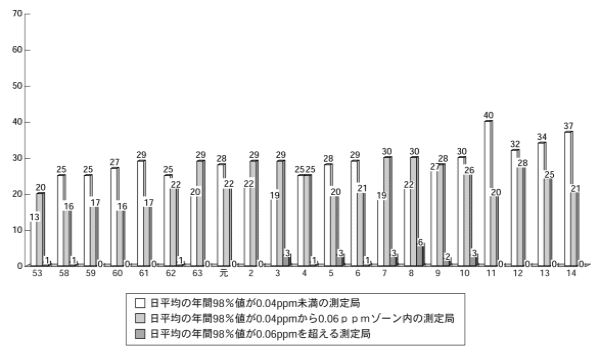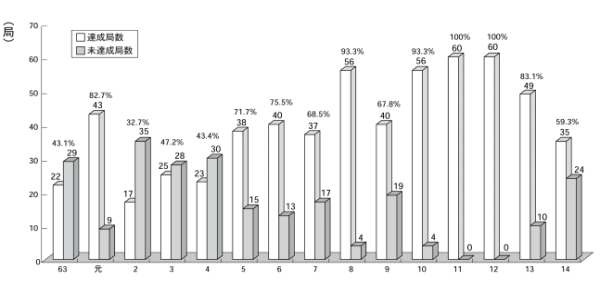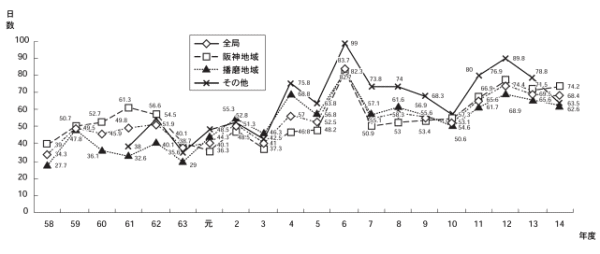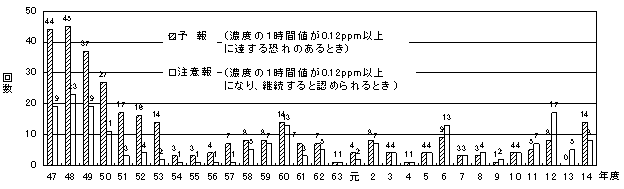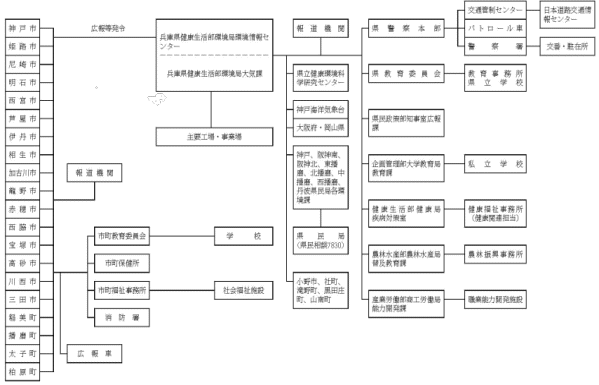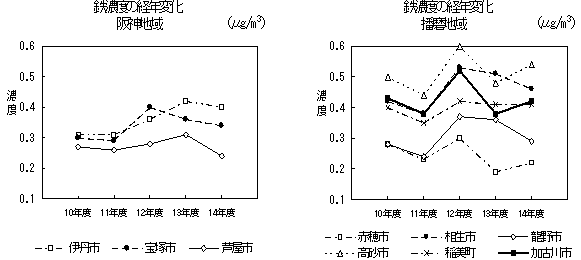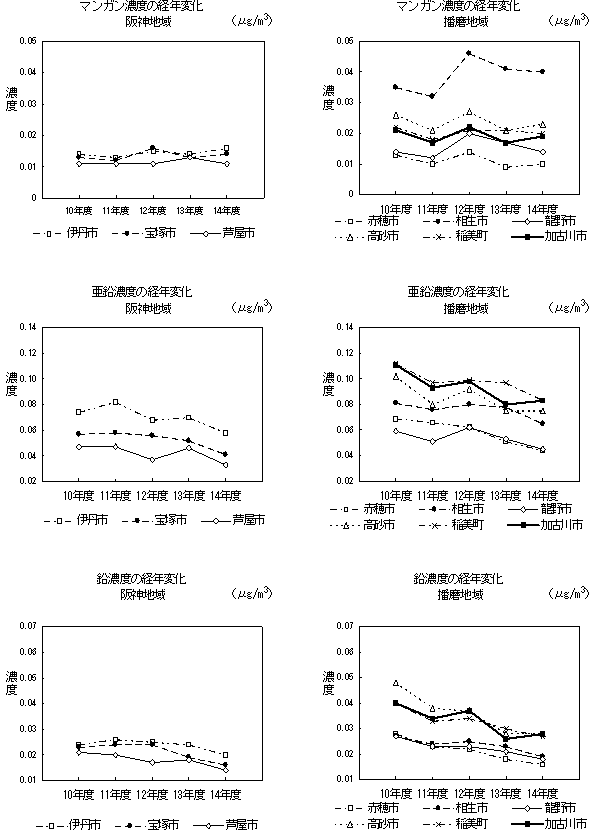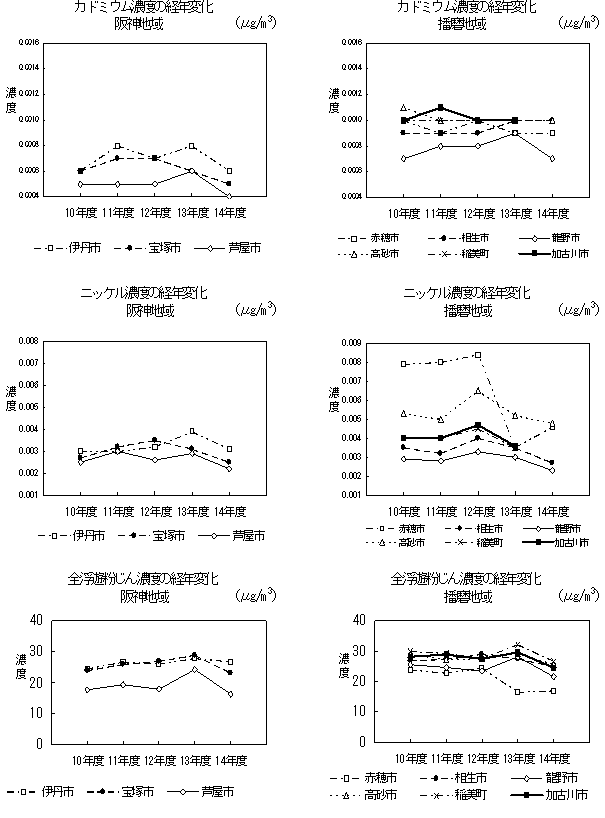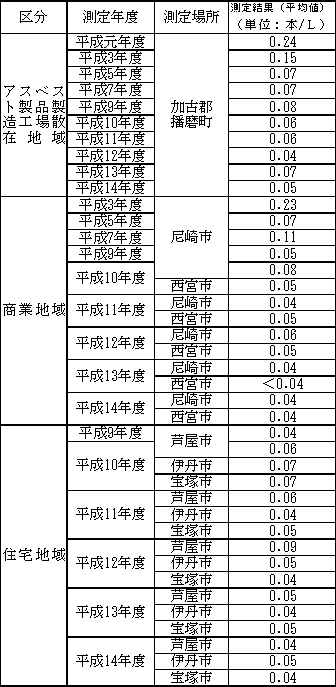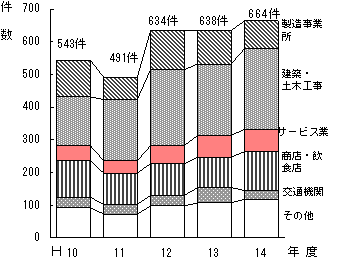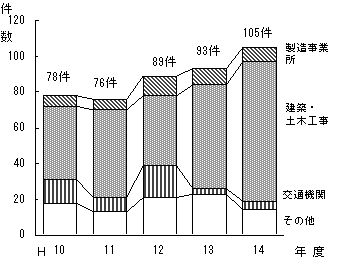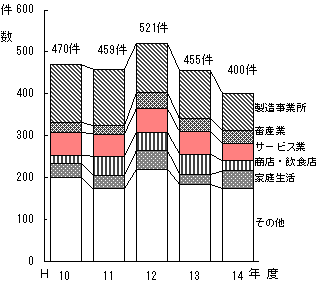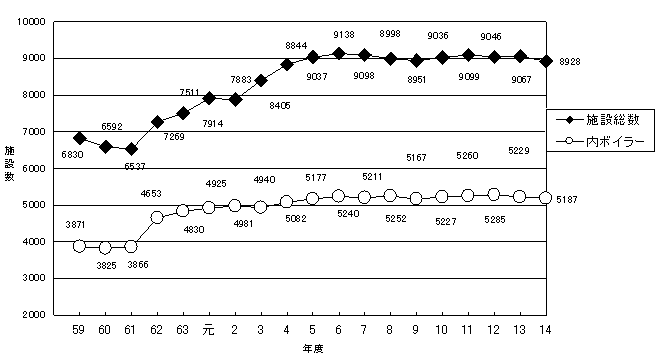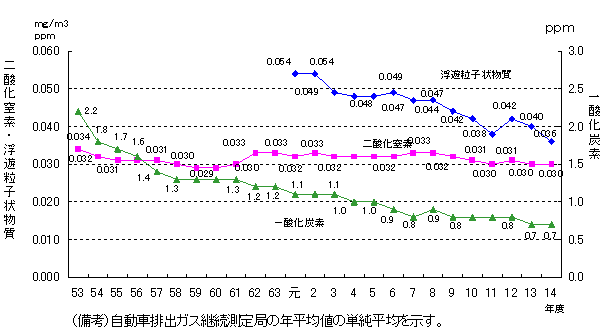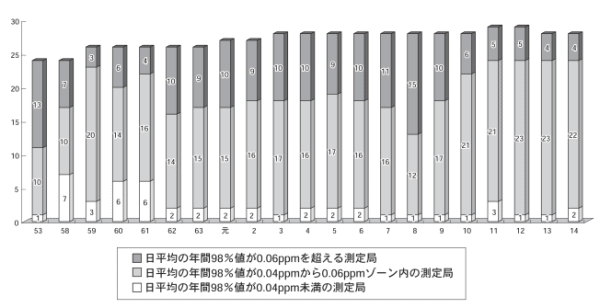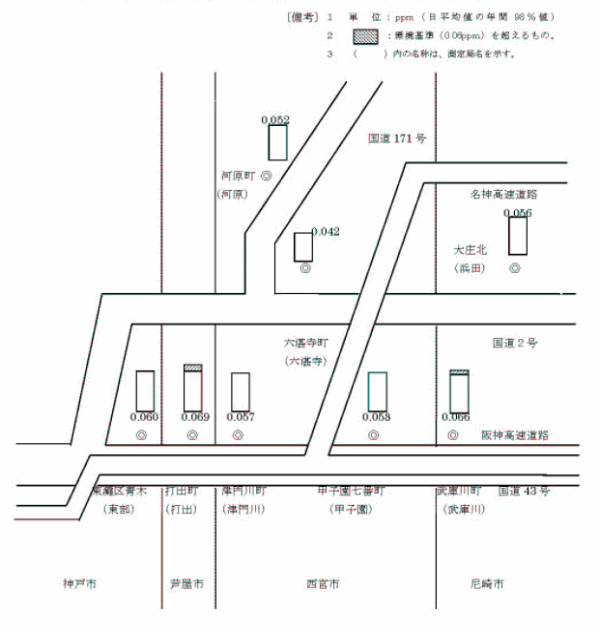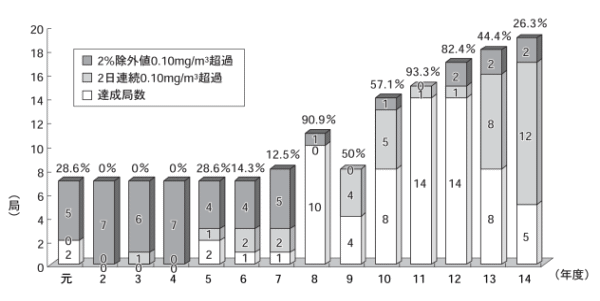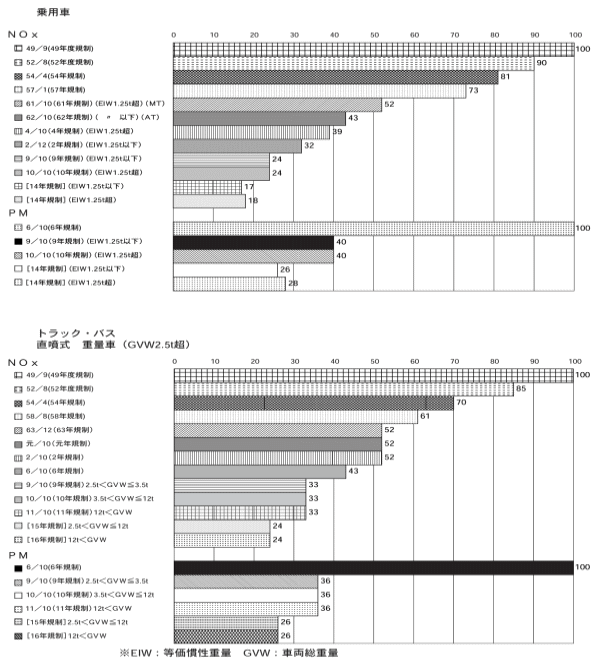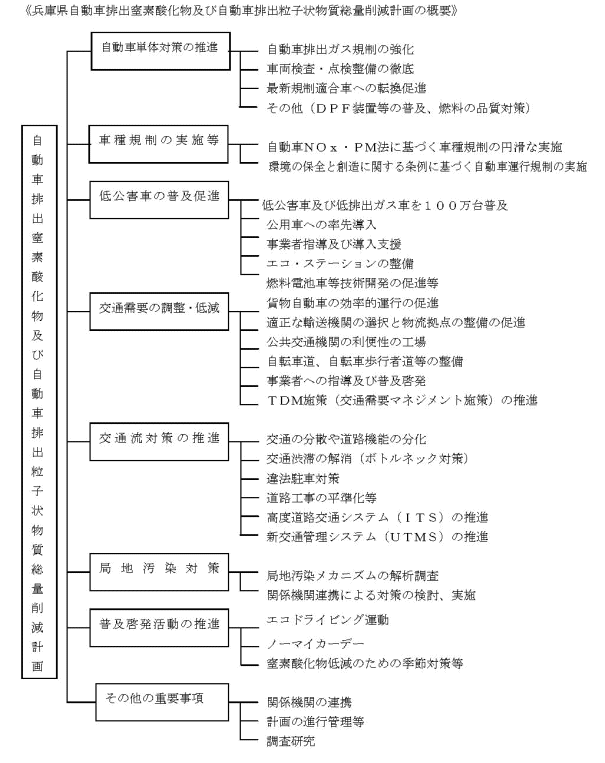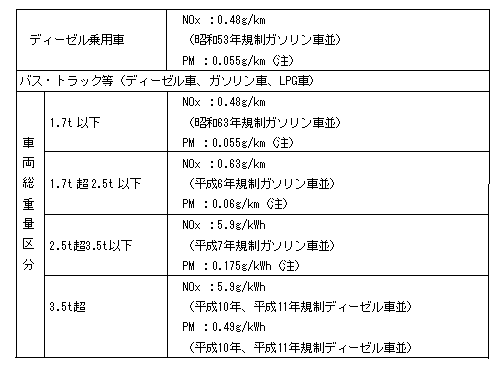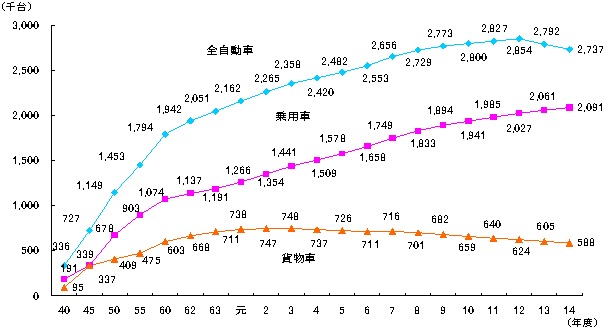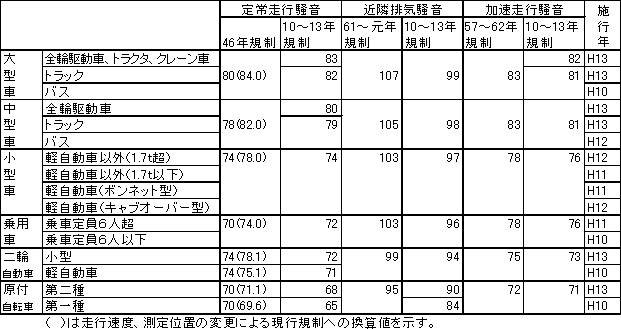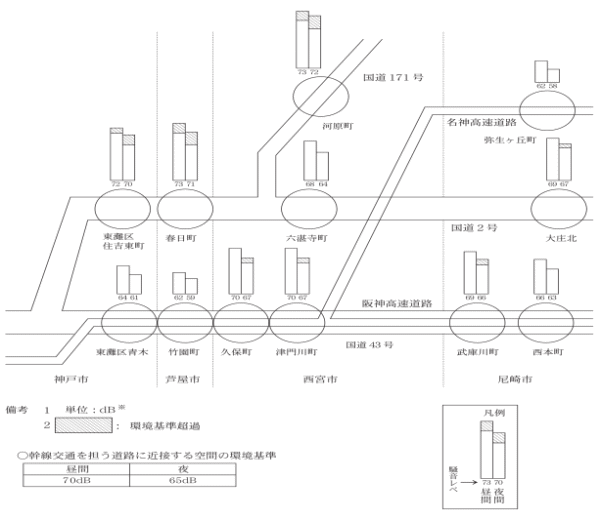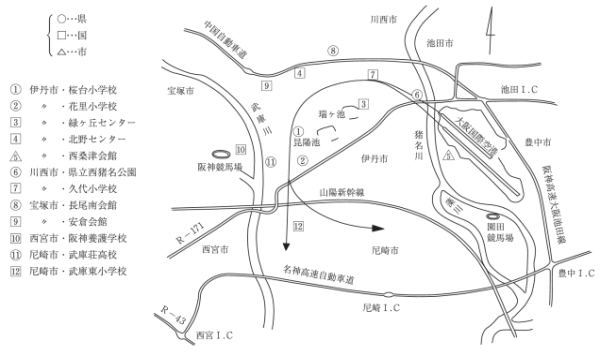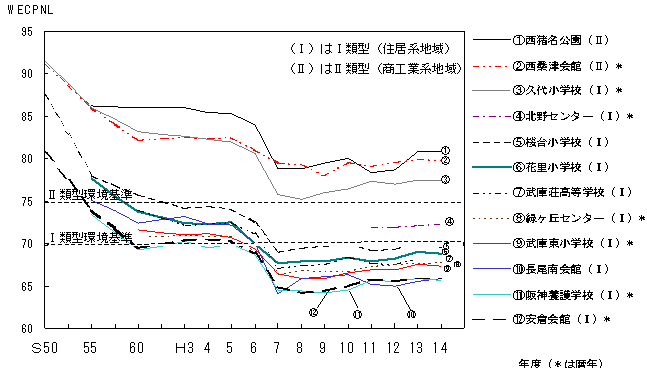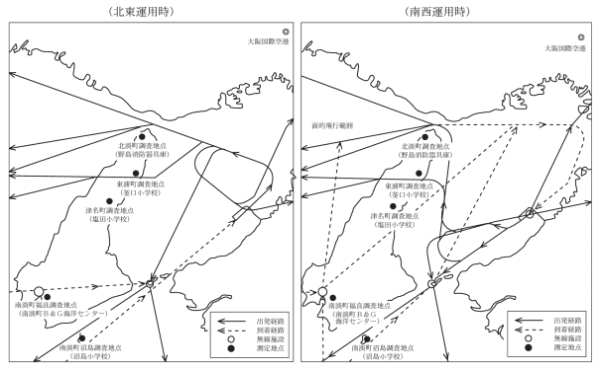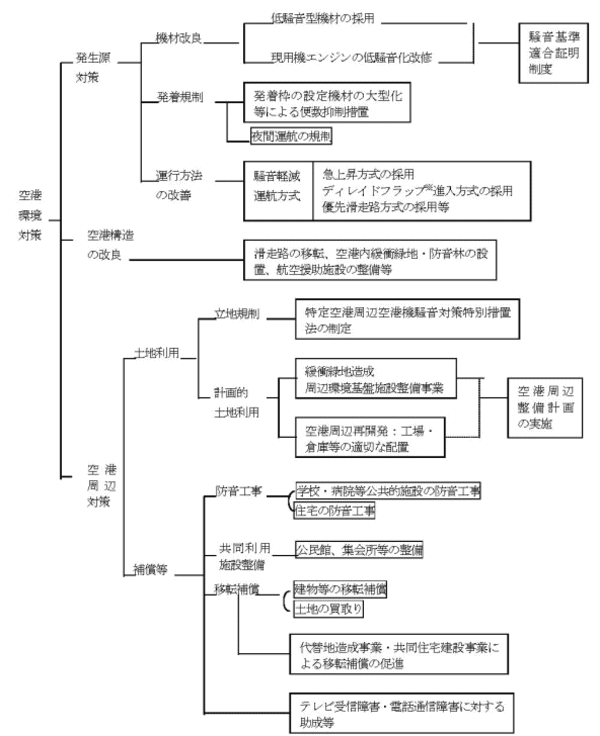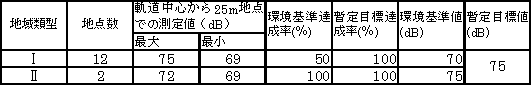第2 一般環境大気
<コラム>騒音問題とは?
<コラム>かおり風景100選
1 二酸化硫黄
二酸化硫黄などの硫黄酸化物は、主として石油・石炭などの化石燃料中の硫黄分がその燃焼過程で酸化されることにより生成される大気汚染物質であり、昭和40年代は、多量の硫黄酸化物が大気中に排出され、スモッグの原因となり、公害の主役であった。しかし、使用燃料の低硫黄化、排煙脱硫装置の設置等の対策により、汚染状況は大幅に改善されている。
(1)二酸化硫黄濃度の推移(資料編第4-5表)
平成14年度の全測定局(58局)の二酸化硫黄濃度年平均値の単純平均は0.004ppmであり、全測定局で環境基準を達成している(平成13年度は三宅島噴火の影響により短期的評価で57局中13局が未達成)。
また、昭和48年度以降継続して測定している局(33局)の年平均値の単純平均は0.004ppmであり、経年変化をみると、近年低濃度で推移している。(第3-1-1図)
(2)二酸化硫黄対策
「大気汚染防止法」に基づく排出規制、阪神・播磨地域(l1市3町)の工場・事業場に対する総量規制、燃料使用基準の適用及び県下主要工場と締結している環境保全(公害防止)協定により、良質燃料の使用、排煙脱硫装置の設置などを指導し、硫黄酸化物の排出量削減に努めてきた。この結果、硫黄酸化物による大気汚染の顕著な改善効果が得られ、すべての一般環境大気測定局で環境基準をはるかに下回る濃度にまで改善された。
しかしながら、最近では廃棄物の燃料化、未利用エネルギーの利用等、エネルギー源の多様化により、発生源の形態が変化しつつあり、今後ともきめ細かな工場・事業場指導等を行っていく。また、気象条件によっては、局地的短期的な高濃度汚染が生じることもあり、的確な監視を引き続き行っていく。
第3-1-1図 一般環境大気汚染の推移
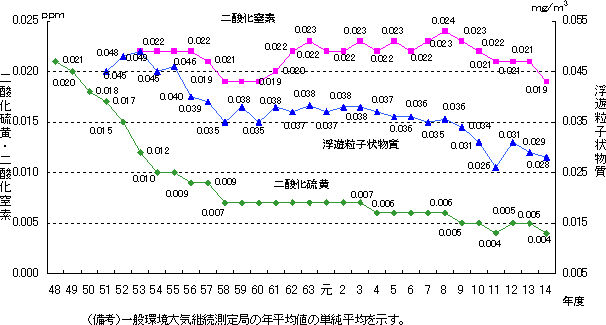
2 窒素酸化物(二酸化窒素)
窒素酸化物とは、燃焼により燃料中の窒素分及び空気中の窒素が酸素と結合して発生する物質である一酸化窒素及び二酸化窒素の総称である。
発生時には、一酸化窒素が大部分を占めているが、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化する。
窒素酸化物の主な発生源としては、工場・事業場、自動車、船舶、ビルや家庭の暖房機器があげられるが、近年、都市部においては、自動車からの排出が大きな割合を占めている。
窒素酸化物のうち、環境基準が定められているのは二酸化窒素であり、人への健康影響のみでなく、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質の一つとされている。
(1)二酸化窒素濃度の測定結果と推移(資料編第4-2表)
平成14年度の全測定局(58局)の二酸化窒素濃度年平均値の単純平均は0.018ppmであり、全測定局(平成13年度は59局)で環境基準を達成している。
また、昭和53年度以降継続して測定している局(36局)の年平均値の単純平均は0.019ppmであり、経年変化をみると、平成9年以降減少傾向にある。なお、平成14年度は浜甲子園局が有効測定時間(6000時間)に満たなかったため、評価対象外としている。(第3-1-1図)(二酸化窒素の経年変化 資料編第4-3表)
(2)窒素酸化物対策
窒素酸化物の発生源は工場・事業場、自動車、船舶など多岐にわたっており、汚染メカニズムも複雑であるため、環境基準を維持達成するためには、発生源別、地域的に効果的な対策を講じることが必要である。
ア固定発生源対策
窒素酸化物対策のうち、固定発生源対策としては、「大気汚染防止法」に基づく濃度規制(ばい煙発生施設の種類・規模別に定められた排出口における濃度規制)及び環境保全(公害防止)協定に基づく排出量抑制指導による低NOxバーナーの導入、燃焼管理方法の改善、燃料の良質化などを強力に推進している。
イ神戸・阪神地域における窒素酸化物対策
神戸・阪神間において、二酸化窒素が高濃度で推移していたことから、平成5年11月30日に「兵庫県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」を策定するとともに、自動車をはじめ工場・事業場、家庭等群小煙源等を含む総合対策指針である「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」を定め、対策を行ってきた。
第3-1-2図 二酸化窒素の環境基準達成状況の推移
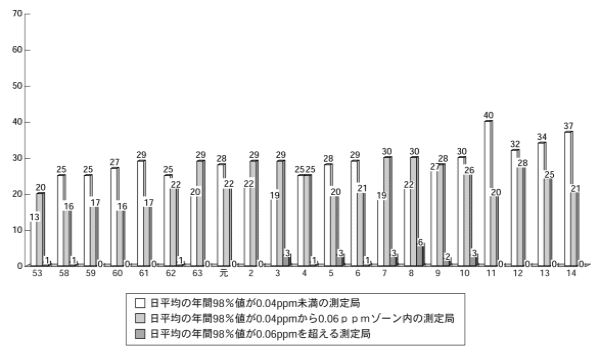
3 浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質とは、物の燃焼などに伴って発生するばいじん、鉱石などの粉砕や自動車の走行に伴って飛散する粉じんなど、大気中に浮遊する粒径10μm(1μmは1000分の1mm)以下の粒子状物質をいう。これらの微粒子は、気道から肺に侵入・沈着し、呼吸器に影響を及ぼすことが知られている。
浮遊粒子状物質は、その生成過程からみた場合、粒子として大気中に放出される一次粒子とガス状物質が大気中に化学的に変化して生成される二次生成粒子とに分類される。また、発生源としては、人為発生源(工場・事業場、自動車等)と自然発生源(土壌粒子、海塩粒子等)とに分類され、粒子の性状(粒径、成分等)が異なる。
(1)浮遊粒子状物質濃度の測定結果と推移(資料編第 4-7表)
平成14年度の全測定局(59局)の浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)の年平均値の単純平均は0.027mg/m3である。
環境基準の長期的評価では、日平均値の年間2%除外値については、全測定局で環境基準値(0.10mg/m3)を達成しているが、日平均値が2日連続で環境基準値(0.10mg/m3)を超過した局が59局中24局となっている。なお、この日は黄砂が観測されている。
一方、短期的評価では、全測定局で環境基準を超過している。
また、昭和51年度以降継続して測定している局(33局)の年平均値の単純平均は0.028mg/m3であり、経年変化をみると、平成元年度以降減少傾向にある。(第3-1-1図)(浮游粒子状物質の経年変化 資料編第4-8表))
(2)浮遊粒子状物質対策
ばいじんについては、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められている。県では、「大気汚染防止法」に基づく排出基準の順守を徹底するほか、環境保全(公害防止)協定による指導などにより、良質燃料の使用及び集じん機の設置など、ばいじん排出量の低減指導に努めている。
粉じんのうち一般粉じんについては、「大気汚染防止法」に基づき、一般粉じん発生施設に係る構造、使用及び管理に関する基準を順守させるほか、「環境の保全と創造に関する条例」により、規制対象施設の拡大、許可制度の導入並びに敷地境界及び地上到達点における濃度規制を行っており、これらを的確に運用することにより、一般粉じんの発生の低減に努めている。
第3-1-3図 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況(長期的評価)の推移
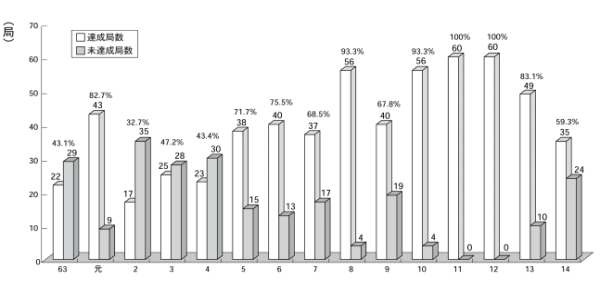
4 光化学オキシダント
光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物、炭化水素等の物質が太陽光線中の紫外線により光化学反応を起こし二次的に生成される酸化性物質の総称であり、オゾン、PAN(パーオキシアセチルナイトレート)等の物質が含まれる。
(1)光化学オキシダントの測定結果と推移(資料編第4-9表)
平成14年度は前年度と同様、全局で環境基準を達成していない。
一般局(53局)の昼間(6時~20時)の1時間値の年平均値は最も高いのが尼崎市北部と神戸市北の0.039ppmであり、全局平均は0.029ppmである。経年変化をみると、平成5年度以降の10年間では0.024ppmから0.031ppmの間で推移している。(光化学オキシダントの経年変化 資料編第4-10表)
また、昼間の1時間値の最高値は加古川市尾上の0.164ppmである。昼間の濃度が0.06ppmを超えた日数の平均(測定局ごとの超過日数の合計を測定局数で割ったもの)は68日であり、前年度と比較して2日減少した。
(2)光化学スモッグ広報等の発令状況(資料編第4-12表)
光化学オキシダントは、紫外線が強くなる夏期に高濃度となりやすいことから県では毎年5月から10月を特別監視期間とし、オキシダント濃度が上昇した場合には光化学スモッグ予報又は注意報等を発令することにより、被害の未然防止に努めている。
光化学スモッグ広報等の発令は、平成14年度は予報14回、注意報8回であり、平成13年度(予報0回、注意報5回)に比べて増加した。
また、平成14年度は平成11年以来3年ぶりに神戸市西区と姫路市において、光化学スモッグによるものと思われる被害が発生したが、いずれも軽症であった。(被害者:神戸市31人、姫路市7人計38人)
(3)光化学オキシダント対策
光化学スモッグによる大気汚染に対処するため、被害の発生防止と被害発生時における被害者の救済を目的として、次のとおり対策を実施している。
ア光化学スモッグ常時監視体制の強化
光化学スモッグ多発期間中(5月1日~10月31日)は、土曜、日曜、祝日を含めた特別監視体制により、光化学スモッグ(オキシダント)の監視を強化する。
イ光化学スモッグ緊急時の広報等の発令及び通報(第3-1-6図)
ウ光化学スモッグ広報等の発令時の対策
(ア)一般県民に対する周知について、報道機関へ協力依頼
(イ)関係機関(警察本部他関係部局)への通報及び事態の周知
(ウ)主要工場(県下約300工場)に対する窒素酸化物排出量の削減要請
及び有機溶剤等炭化水素類の使用を可能な限り抑制することの要請
(エ)広報等発令地域への車両の乗り入れ自粛の呼びかけ
エ健康被害発生時の救急医療体制を県医師会へ協力要請
オ神戸海洋気象台との気象情報交換の緊密化
第3-1-4図 昼間の光化学オキシダント濃度が
0.06ppmを超えた日数の平均の推移
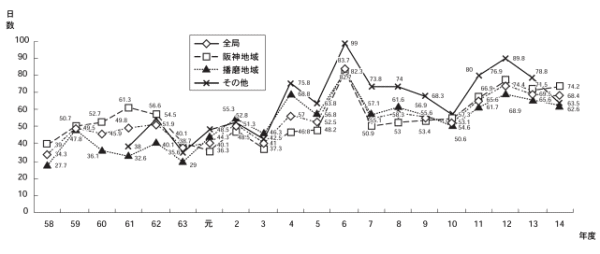
第3-1-5図 光化学スモッグ広報等発令回数
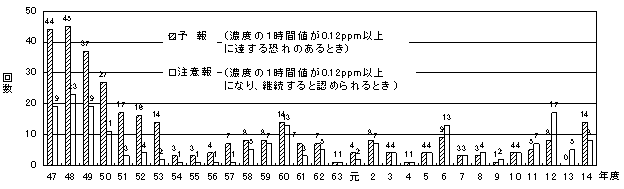
第3-1-6図 光化学スモッグ広報等連絡系統図
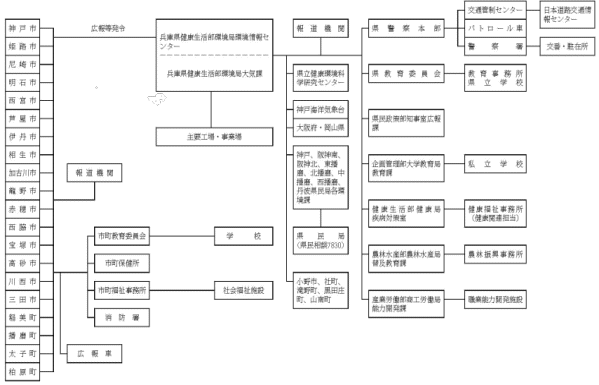
5 有害大気汚染物質
低濃度であっても長期的曝露によって健康影響が懸念される有害大気汚染物質について、健康影響の未然防止を図るため、大気汚染防止法が改正され、平成9年4月から施行され、同法第18条の23及び第22条の規定に基づき、一般環境について5地点、固定発生源周辺について2地点、道路沿道1地点での測定を行った。
(1)測定物質
優先取組物質として位置づけられた22物質のうち、既に測定方法の確立されている次の19物質について測定した。
①アクリロニトリル②アセトアルデヒド③塩化ビニルモノマー④クロロホルム⑤1,2-ジクロロエタン⑥ジクロロメタン⑦テトラクロロエチレン⑧トリクロロエチレン⑨ベンゼン⑩ホルムアルデヒド⑪1,3-ブタジエン⑫酸化エチレン⑬ニッケル化合物⑭ヒ素及びその化合物⑮マンガン及びその化合物⑯クロム及びその化合物⑰ベリリウム及びその化合物⑱ベンゾ[a]ピレン⑲水銀及
その化合物
なお、固定発生源周辺、道路沿道については、上記のうち排出が予想される物質とした。
(2)測定期間、頻度
毎月1回測定を実施した。
(3)結果
結果を資料編第4-15表に示す。
このうち4種類の物質について環境基準が定められており、それらを年平均値で評価すると、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンのいずれもすべての地点で環境基準を達成している。
平成15年7月31日に中央環境審議会より今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第7次答申)が示され、環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るため、優先取組物質のうちアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物の4物質についての指針となる数値が設定された。
この指針値は、大気モニタリング調査結果の評価にあたっての指標や事業者による排出抑制努力の指標として定められたものである。
(指針値)
| アクリロニトリル |
年平均値 2μg/m3 以下 |
| 塩化ビニルモノマー |
年平均値 10μg/m3 以下 |
| 水銀 |
年平均値 0.04μgHg/m3 以下 |
| ニッケル化合物 |
年平均値 0.025μgNi/m3 以下 |
(4)有害大気汚染物質対策
数多くの化学物質が開発され、いろいろな分野に利用されており、大気中からも低濃度ではあるが種々の物質が検出されている。
それらの中には、長期間の暴露による健康への影響が懸念されるものもあるため、健康影響の未然防止の観点に立って着実に対策を実施していくことが必要となっている。
こうした状況にかんがみ、有害大気汚染物質のうち、特に健康に影響を及ぼすおそれ(健康リスク)が高いと評価されたベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、「大気汚染防止法」に基づき、指定物質に指定され、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準が設定されている。
県では、これらの物質を使用する工場・事業場に対し、排出抑制指導を行っている。
6 金属物質等
県下における金属物質の現況を把握するため、大気中金属物質を県下9地点で測定し、県南部地域における金属物質による大気汚染の状況を監視した。(資料編第4-16表)
(1)測定物質
①鉄②マンガン③亜鉛④鉛⑤カドミウム⑥ニッケル⑦全浮遊粉じん
(2)測定地点
伊丹市役所、加古川市役所、赤穂市役所、高砂市役所、宝塚市老人福祉センター、芦屋市朝日ケ丘小学校、相生市役所、龍野市役所、稲美町役場
(3)測定結果
全浮遊粉じんに含まれる金属物質濃度の経年変化を阪神地域、播磨地域に分類して第3-1-7図に示す。
全浮遊粉じんについては、長期的な濃度推移の傾向をみると、昭和58年度以降横ばいもしくは漸減傾向を示している。前年度と比較すると、赤穂市及び伊丹市では横ばい状態、その他7地点では減少に転じた。
各金属成分についての、長期的な濃度推移の傾向をみると、昭和58年度以降横ばいもしくは漸減傾向を示している。また、前年度と比較すると、マンガンは5地点、鉄は3地点、ニッケル、鉛及びカドミウムは1地点において前年度より濃度が増加したものの、その他は横ばいもしくは減少傾向を示した。
こうしたことから、今後も地域的な大気汚染物質の負荷量及び景気変動に伴う経済活動の変化を注視し、継続的な監視が必要である。
(4)金属物質等有害物質対策
有害物質については、「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設の種類ごとにカドミウムなど4物質について規制基準が定められている。
また、28物質の特定物質については、事故時の応急措置及び速やかな復旧義務が事業者に対し課せられている。
県においては、これら「大気汚染防止法」に基づく規制基準の順守を徹底するとともに、「環境の保全と創造に関する条例」において、有害物質に係る特定施設として溶剤洗浄施設等に届け出義務を課し、クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレンなど29項目の有害物質について、地上到達地点濃度、敷地境界線上濃度の規制を工場等に対して行い、排出抑制の指導を行っている。
また、県下南部9地点における大気中金属物質(7項目)の監視を引き続き実施し、大気中の金属物質による大気汚染の実態把握に努めている。
第3-1-7図 各金属成分濃度の経年変化
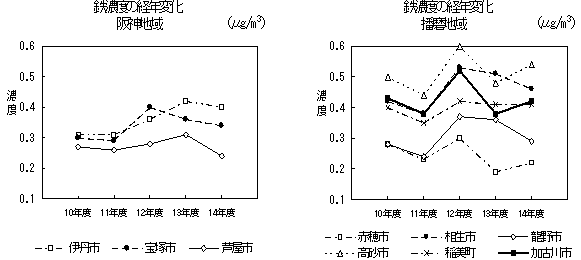
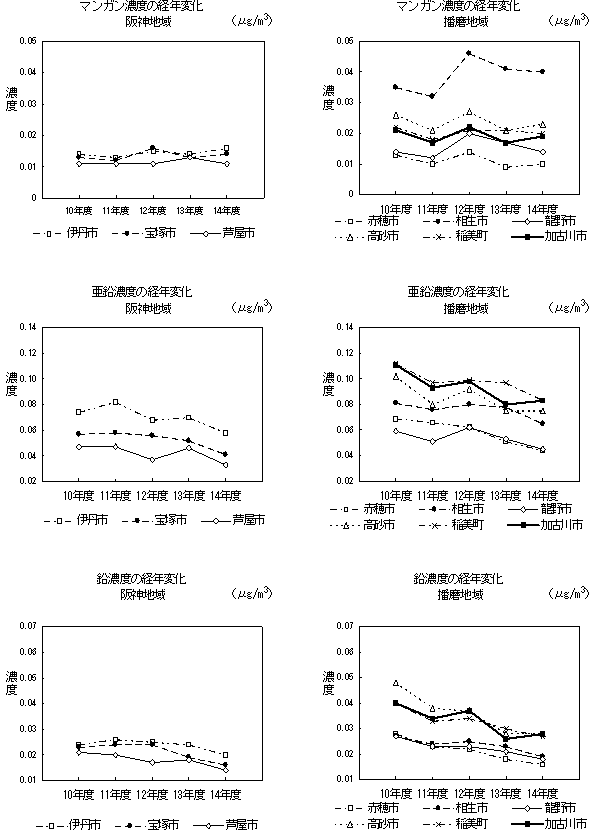
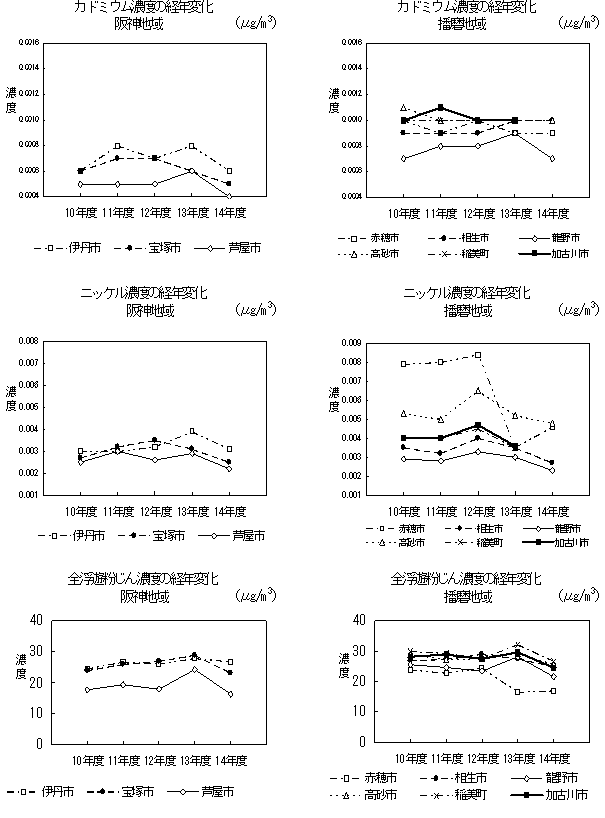
7 アスベスト
過去、アスベスト問題は、主にアスベスト製品製造工場等での労働環境問題としてとらえられ、高濃度暴露による石綿肺、肺がん、悪性中皮腫などの健康被害を防止する目的で労働安全衛生の面から種々の対策が講じられてきた。
しかし、一般環境中にもアスベストの存在が確認され、各種発生源に対する排出抑制対策が必要であることから、一般環境及びアスベスト製品製造工場の監視調査を実施している。
なお、一般環境等のモニタリングをアスベスト製品製造工場散在地域、商業地域及び住宅地域において実施してきた結果は第3-1-3表のとおりである。
平成14年度調査では、各地域ともほぼ同じような値を示し、特に高い値はみられなかった。また、経年的には低下傾向がみられる。
第3-1-3表 兵庫県のアスベスト一般環境等モニタリング結果
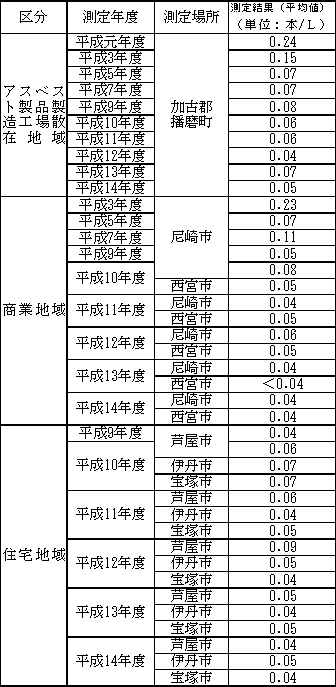
8 騒音・振動
(1) 14年度の騒音苦情
騒音は、住民にとって最も身近な公害である。そのため、平成14年度の苦情件数は664件と多く、全公害苦情件数の18%を占めている。
発生源別の苦情件数の経年変化は第3-1-8図のとおりである。主な苦情の発生源は、建築・土木工事、商店・飲食店、製造事業所であり、これらの業種で全体の約67%を占めている。
騒音苦情が最も多い建築・土木工事では、建設機械の構造や作業の性質上、防音対策が困難な場合が多く、また、工事現場に出入りする車両による迷惑感も苦情の原因となっている。
騒音苦情の第2位は商店・飲食店であり、その中ではカラオケ騒音が約40%を占めている。
騒音苦情の第3位は製造事業所であり、鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造業が主な原因となっている。
第3-1-8図 騒音苦情件数の推移
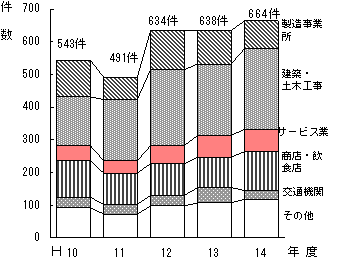
(2) 工場・事業場及び建設作業の騒音規制
「騒音規制法」及び「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、工場・事業場及び建設作業から発生する騒音を規制する地域として、県下全市町の全域を指定している。
工場・事業場から発生する騒音については、騒音発生源となる圧延機械などの施設を届け出の対象とし、地域ごと、時間帯ごとの区分に応じた音の大きさで規制を行っている。
建設作業の騒音については、くい打ち機を使用する作業などを届け出の対象とし、作業時間などの規制を行っている。
商店・飲食店から発生する騒音については、「環境の保全と創造に関する条例」によって音の大きさによる規制に加えて、飲食店の深夜における営業の制限、また、カラオケ騒音に対しては、音の大きさによる規制とともに、県下22市29町において深夜における音響機器の使用の制限を行っている。
なお、法律に基づく規制対象施設等の届け出数は資料編第3-2表のとおりである。