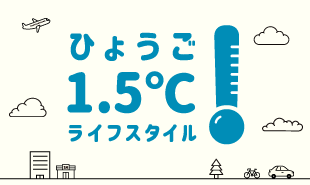第1節 県立健康環境科学研究センター
第1 酸性雨・酸性霧の生態系および建築物・文化財への影響に関する研究
酸性雨・雪・霧等の湿性沈着物とガスならびにエアロゾルの乾性沈着を含めた酸性沈着の実態把握を行うとともに、森林生態系への影響を解明するために実施した。
(1)降水については県下3地点(神戸須磨、豊岡及び柏原)で、霧については六甲山で試料採取を行い継続的にデータを蓄積している。降水のpHは横ばいもしくは低下する傾向が見られた。霧については平均pHは3.70であり、前年に比べ約0.2低下した。一方、乾性沈着については4段ろ紙法により、神戸須磨で大気中ガス及びエアロゾルの採取・分析を行った。神戸須磨は全国と比較して、ガス成分、エアロゾル成分ともに高濃度であった。また、乾性沈着速度の算定手法を検討中である。
(2)山岳地では標高が高くなるにつれ、霧の発生頻度が高く酸性沈着量も増加する。このことから、標高別による林内への酸性沈着物量と土壌呼吸代謝量の測定を行うことで土壌微生物の活性度との関係すなわち根圏環境と樹木衰退との関連を見た。その結果、窒素成分濃度ならびにH+イオン濃度は標高とともに増加した。一方、塩基カチオン(Ca,Mg,K)濃度は標高とともに減少した。これら林内土壌への酸性沈着の降下によりもたらされるNの過剰、塩基の溶脱が、土壌微生物層を悪化させ、樹木の生育障害を引き起こす一因になっていると考えられた。
(3)六甲山のスギ林において、林内雨と土壌溶液を採取し、森林にもたらされる霧水沈着が土壌溶液の化学組成や土壌の酸性化に及ぼす影響について検討した。土壌溶液のH+及びT-Al濃度はスギ林において国内で報告された値を上回った。林内雨と土壌溶液のイオン成分濃度の比較から、845m地点における森林土壌に対しては、酸中和能を上回る酸性沈着が霧水によってもたらされており、林内雨はほとんど中和されていないことが示された。
第2 自動車公害の実態把握と汚染特性の解明に関する研究
自動車公害、特にディーゼル排ガスによるPM2.5微粒子の実態把握と生成機構ならびに大気汚染と騒音・振動対策の複合効果等について検討している。
(1)PM2.5の長期間平均値を測定するためのサンプラー(LongTermAverage2.5、以下LTA2.5と略す)を試作し、その性能を調べた。9カ月間、サンプリング時間の違いによる測定値への影響について検討した。2台のLTA2.5を使い、1台は2週間(LTA2.5-A)、もう1台は3または4日間(LTA2.5-B)のサンプリングを行ったが、LTA2.5-Aの値と、LTA2.5-Bの2週間平均値に有意な差は認められなかった。硫酸塩濃度についても測定値間に有意な差が認められず、アーティファクト(採取時における人為的誤差)の影響はみられなかった。期間を通してのPM2.5濃度範囲は11.5~30.5μg/m3であった。LTA2.5は3段階分級をしているのでPM10濃度も得られる。PM2.5/PM10は0.6~0.7の範囲内で変動していたが、3月から4月にかけては黄砂の影響でPM10濃度が上がったため、比率が0.3前後まで低下した。硫酸塩濃度範囲は2.4~6.3μg/m3、PM2.5に占める割合は17~36%の範囲で、主要な成分の一つであることが分かった。硝酸塩濃度は硫酸塩濃度よりも低く0.19~3.0μg/m3、PM2.5に占める割合は1.2~15%であった。
(2)オゾン化学発光法を測定原理とする硝酸ガス自動測定機の開発において、新たに微粒子除去装置を考案した。本装置は妨害ガスの影響が無いため、より正確に(定量下限は1ppb)より長期間(1カ月)、硝酸ガスをリアルタイムで連続測定することが可能になった。
(3)国土交通省は、平成12年、平面一般道路の騒音対策として、高さの低い低層遮音壁の導入を提言した。本壁は、運転者・歩行者の視野、建設の難しさ、日照阻害などの問題も生じないことから普及しつつある。本壁の設置個所で騒音対策効果を調べた。測定点は、国道2号4車線道路で大型車の混入率は50%を超えている。遮音壁による挿入損失を測定するため、高さ1m、幅約16mの壁の裏側中央、及び約9m離れた壁と壁の間で調査した。等価騒音レベルの範囲は60‐70dBであった。壁による挿入損失の幅は2.7~3.8dBで、平均は3.2dBであった。この値は、車道と測定点の位置関係から変動するため普遍的ではないが、高さ1mの壁であっても国道43号沿道における緑地帯の効果とほぼ同程度の効果があることを示している。
第3 兵庫県における温室効果ガスの削減対策と県民生活への影響予測に関する研究
温室効果ガスの排出量を見積もるとともに、その削減方法を提示し、もって県民の削減行動に科学的根拠を与える資料を提供することを目的として実施した。
(1)兵庫県における過去4年間の排出量を見た場合、瀬戸内海沿岸地域からの排出量が全県下の57%を占めており、神戸市の排出量は平成8年の18,374kt-CO2/年から平成11年の19,447kt-CO2/年へと増加傾向にあった。また、神戸市内では発電所の新設や阪神高速の延長など新たな増加要因もあり、さらに詳細な推計が必要となっている。
(2)兵庫県下の亜酸化窒素(N2O)およびメタン(CH4)濃度の変動調査については、N2Oの発生源調査と環境濃度の長期モニタリングに関して、これまで精度の高い測定を実施してきたが、公的機関が保証する標準ガスが存在しないため、測定精度の高さを実証できなかったが、本年度は国立環境研究所との間で標準ガスを相互に比較測定した。
(3)温室効果ガスの中で、近年濃度増加が注目されている物質に対流圏オゾンがある。対流圏オゾンは都市部においてはオキシダントと等価に評価され、兵庫県のみならず全国的に平成元年以来増加の一途をたどり、関東では人的被害が報告されるに至っているものの、その生成原因については明確になっていない部分が多い。対流圏オゾンの起源について、洋上調査の結果をもとに検討を行った結果、冬場は大陸方面から日本への対流圏オゾン移流量が多いが、夏場は少ないことが明らかにされた。
第4 瀬戸内海沿岸の環境浄化能・汚濁蓄積特性の評価及び経済的環境評価に基づく環境保全・創造施策の提言に関する研究
各種の汚濁物質の排出に伴う海域の水環境汚染は、環境基準・排出基準等の設定・強化により一定の改善がみられるものの、汚濁負荷量の削減と水質改善との関連は明確でなく、依然として赤潮の発生・底層貧酸素化が観測されている。近年、これらの現象の解消にとどまらず、更に良質な海域環境の創造が求められている。このため、河川流域・海域の水環境要素の関連を明らかにし、流域・海域の適切な管理が必要となっている。これらの水環境要素と水質・生態系との関係を解明し、良好な水管理の方策を見いだすことを目的として本研究を実施した。
1 干潟・砂浜・藻場・人工海岸等が生態系・水質保全に果たす役割の解明
沿岸域における干潟・砂浜・藻場等は、生物活動が盛んなことに由来する有機物分解能、及び窒素・燐除去能に由来する高い水質浄化能から環境保全上重要とされている。これらの水質浄化能の評価のため、尼崎港内において実験的に造成された干潟干潟において二枚貝(アサリ)による窒素、燐の固定を検討した。3月の養成開始以後7月までは、高い生残率を示し、殻の大きさおよび湿重量は経時的に増加し、順調な成長が見られた。栄養塩の主要な固定部である軟体部については、軟体部乾燥重量から抱卵、産卵期と考えられる4月、7月に高くなり以後低下した。しかし、8月の貧酸素化水塊の到来により個体群の大幅な減少が見られたが、9月からは殻長10mm程度の稚貝が見られ始めた。この稚貝について、追跡調査を行ったところ、平均湿重量が4.2倍となり、生残率についても良好であった。このことから、尼崎港内でアサリの生育に必要な場(干潟)を造成すれば、貧酸素化を克服することによりアサリの年間をとおしての生活史が完成すること、また、浮遊幼生の着底、稚貝の成長による再生産が可能となることからアサリによる水質浄化が可能となることが示された。
2 貧酸素水塊の発生機構とその未然防止対策の検討
尼崎港内において実験的に造成された干潟における硫化物と強熱減量について調査した。貧酸素化が見られない造成直後の3月から6月については硫化物は検出されなかったが、貧酸素化が見られ始めた7月から検出され始め8月には0.079mg/gに達した。また、強熱減量は7月まで緩やかな増加が見られたが、8月には減少した。これらのことから、貧酸素化に伴い、底質環境は急速に悪化し、アサリの大量死を招いたと考えられた。貧酸素化による底質環境の悪化防止がアサリ等の底生生物の生存、さらにはこれらを利用した水質浄化には不可欠であることがわかった。
第5 河川水質の改善、水量の確保、水辺空間の保全に向けた面源負荷の削減対策や適切土地形態の提言に関する研究
流域の適切な水環境保全のため、河川水質を決定する流域の各種の要因とその負荷量を把握することを目的として、山林集水域や農村集落排水からの汚濁物質の流出特性を解明するため本研究を実施した。また、水性生物の棲息状況からみた水質環境を評価することを試みた。
1 山林集水域からの汚濁負荷流出機構の解明と評価
生野町にある山林集水域の渓流河川で週1回の頻度での定期調査と、自動測定・採水システムによるハイドログラフに沿った降雨時調査を実施し、主要溶存無機イオン等の分析を行った。区間代表法により算出した降雨時を含む年間NO3-N流出負荷量は3.2kg/ha/yearとなり、週1回の定期調査から算出した年間流出負荷量はそれの0.6倍と過小評価された。その他の項目では0.8倍となった。週1回、隔週、2週間隔、月1回と調査回数を変えた場合の年間流出負荷量を推定すると、調査回数の減少と共にその変動が大きくなり、年間流出負荷量の見積もりにおいて採水頻度の影響が大きことが示された。また、構築した自動採水システムによる降雨時調査を1年間実施した。日降水量8.5~101.5mmの範囲の降水日について計41回の採水が実施できた。これまでの方法では困難であった多くの降雨時データが得られたとともに、降水量と山林域からの降雨時T-N流出量およびT-P流出量の間にそれぞれの対数値で正の相関関係が認められた。降雨量から流出負荷量を算出する方法に適用可能であることが分かり、当該山林集水域からの年間流出負荷量は窒素で4.27kg/ha/年、リンで0.11kg/ha/年と算出でき、精度の高い年間流出負荷量が求められた。
2 農村を流れる小河川の栄養塩流出特性の解明と評価
農繁期を中心に降雨が水質に与える影響を調べた。その結果、田植え後の大きな降雨の直後には、汚濁負荷量は田植え前の降雨の少ない時期に比べ、数倍の値を示した。また、降雨後の汚濁負荷量の下流への変化は下流へ行くに従い、増加していった。一方、田植え前の少雨時には水田に河川水が利用されているためか、河川の流量及び水質負荷量は中流部で少なくなる分布を示した。
3 底生動物群集による水環境評価
揖保川および林田川下流の底生動物群集の回復について検討し、河川水に微量のT-Crが検出され、皮革排水の流入がうかがわれたが、原因は不明であった。下水道普及率が70%前後であり、生活排水の影響も底生動物群集の回復に影響していることが考えられた。
第6 不測の環境汚染事故等に備えるための危機管理機能の強化に関する研究
水圏生物へのダメージ、廃棄物の不法投棄、住民の不快(悪臭・頭痛・吐き気等)、地震等による突発的負荷の増加による環境汚染等に関する事例を収集し、調査方法、対応策等のデータベースを作成し、事故時の効率的な初動体制に資することを目的とした。
1 油汚染に対する生物学的環境修復技術の評価
油汚染に対する生物学的環境修復技術導入のために国が作成したガイドラインの検証を行った。土着微生物による重油分解実験では窒素、肥料を添加することにより、油分解が促進されるが、肥料の施肥による環境への影響は藻類増殖試験(AGP試験)の結果から認められなかった。これらの結果から、土着微生物による油分解の有効性と安全性が確認された。また、都市河川中の油汚染は発生源の特定が難しい。そのため、油種を迅速に同定する分析法を検討し、発生源の特定を行った。
2 廃棄物の不法投棄による環境汚染の評価方法の検討
廃棄物不法投棄対応マニュアルを作成するため、吸水性樹脂を用いた水試料の濃縮法と蛍光X線法により、不法投棄廃棄物溶出液中重金属の一斉・迅速分析法を検討し、実用化した。廃棄物最終処分場、事業場を調査し、浸出水の分析を行った。
3 有害物質の出現に対する効果的な取り組みの検討
排出が懸念される汚染物質は、PRTR情報に基づき、地域ごと、事業場ごとの有害物質排出量を予測するためのデータベース化を検討した。平成13年度PRTR情報のACCESSによるデータベース化を図った。
4 危機管理体制強化のためのデータベースの作成
近隣各自治体に問い合わせて、大気汚染等被害発生時対応要領、過去の事故対応事例等のデータを収集し、緊急時対応事例を解析した。
第7 「兵庫県ダイオキシン類削減プログラム」に基づく各種対策の削減効果の数値的検証及び新たな施策の提言に関する研究
1 県下の高濃度検出個所についての原因把握
これまでのモニタリングにおいて、環境基準はクリアしているものの、相対的に高い濃度が観測されている地点を対象として詳細調査を実施した。大気高濃度地点については、建築物に使用されているシーラントに含まれるPCBが高濃度の原因であることを明らかにし、河川については、かつて使われていた農薬中の不純物が原因になっていることを示した。
2 ダイオキシン類の精密分析と臭素化ダイオキシン類の分析法の検討
現モニタリングでは測定することになっていない低塩素化ダイオキシン類や毒性係数が示されていないその他の異性体を含めた詳細なダイオキシン類を分析することによって、地域や地点による汚染原因の違いを明らかにする結果を得た。また、PCBについても精密な異性体分析条件の検討をし、全209異性体を193本のピークとして分離できる、より精密な異性体分析方法を開発した。
臭素化難燃剤であるポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)およびポリ臭化ビフェニル(PBB)の分析条件の検討を行い、環境中での異性体分析方法を確立した。PBDEについては、環境大気、底質、魚試料等にて異性体分析を行い、6臭素化以下の同族体が環境中に残留していることを明らかにした。
3 地域の汚染実態をより正確に把握するための調査手法の開発
ダイオキシン類の大気モニタリングでは、これまで行われてきた24時間採取では気象条件等の影響から日間変動が大きく、リスク評価の面から不十分であることを明らかにし、ローボリュムエアサンプラーによる長期連続サンプリング法の有効性を提唱し、公定法化につながることになった。
4 ダイオキシン類濃度予測のためのシミュレーションモデルの構築
数値予測手法を用いたダイオキシン濃度予測モデルを構築した。発生源情報や気象条件を最新のデータを入力することによって、地域ごとの大気中ダイオキシン濃度予測への利用を試みている。
第8 生体試料によるダイオキシン類暴露モニタリング
母乳中ダイオキシン類の濃度の推移を把握し、体内ダイオキシン類を減少できるライフスタイルを見出すとともに、地域生態系の汚染度とその推移を把握することを目的として研究を行った。これまで、「ダイオキシン類に係る生物及び生体試料取扱いマニュアル(案)」を策定し、母乳中脂肪酸組成とダイオキシン類の関係を統計解析し、環境中とヒト試料中のダイオキシン類異性体分布、および母乳中PCB類濃度の変動要因について検討した。母乳・ヒト脂肪組織中および環境中のダイオキシン類異性体分布を比較したこれら一連の研究から、ヒト生体内で比較的多く見られる異性体、すなわち代謝を受けにくい異性体の存在が確認された。
第9 有害化学物質の排出・移動情報(PRTR)と環境モニタリングデータとの整合性の評価及び発生源インベントリー(目録)の整備に関する研究
1 PRTR法指定物質の挙動および環境リスク
PRTR法指定物質で界面活性剤である直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩について、LC/MS法を用いた高精度でシンプルなモニタリング法を開発するとともに、これまでのモニタリングデータをもとに、陰イオン界面活性剤の河川環境での環境リスク評価を行った。その結果、魚類に対する各種リスクは過去10年間で確実に減少していたが、忌避行動に関しては、県内の半数近い地点で現在も高リスク状態にあることがわかった。
環境ホルモン物質の一種でもあるビスフェノールAおよびノニルフェノールについては、県内河川水中の濃度分布を把握するとともに、invivo実験結果をもとに環境リスク評価を行った。ビスフェノールAおよびノニルフェノールの検出率は、それぞれ54%および46%であったが、魚類の内分泌撹(かく)乱に関する最低影響濃度(LOEC)に対し、検出濃度は高い場合でも0.1であり、これらの物質の環境リスクは現時点では高くないことがわかった。
上記物質を含む主な環境ホルモン物質について、高濃度を示すことの多い都市河川で詳細な調査を行い、これらの物質が、底質の微細粒子中に高濃度で含まれることを明らかにした。
2 河川中農薬のモニタリング
県下の代表的河川である加古川の下流域3地点(大住橋、美の川橋、上荘橋)において、9月から11月の間の3カ月間、人の健康の保護に関する環境基準値やゴルフ場農薬等で指針値が定められている農薬のうち、GC/MSにより一斉分析が可能な57種の農薬の検出状況を調査した。その結果、計17種の農薬を検出し、特にイソプロチオラン、フルトラニル、シメトリン、フェノブカルブの検出頻度が高いことが明らかになった。調査時期別に農薬濃度と検出農薬数の変動をみると、農薬濃度は9月を最大に順次減少するのに対し、検出数は10月をピークとした山型を呈していた。すなわち、10月に低濃度ではあるが他種類の農薬が一時的に検出されたことが示された。
3 有害化学物質の分析法開発
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」において、第1種特定化学物質に指定されたN-モノ(ジ)メチルフェニル-N'-モノ(ジ)メチルフェニルパラフェニレンジアミンの分析法(河川水・海水、底質、魚中の含有量)を開発し、環境中での存在状況の調査を行った。現時点では、ppb濃度レベルでは環境試料中では検出されていない結果であった。
4 大気中揮発性有機化合物の濃度とその評価
PRTR法第一種指定化学物質を含めた多種揮発性有機化合物の同時測定について分析条件等の検討を行い、確立した分析法により大気中揮発性有機化合物の測定を行った。測定結果とPRTRパイロット事業による排出量等報告データとの比較を行い、おおむね大気中濃度とPRTR報告データとは相関がある結果が得られた。
第10 廃棄物処分場等処理施設に関する信頼性の高い管理指針の策定に関する研究
1 蛍光X線を用いた重金属類の迅速分析
廃棄物の溶出試験液を迅速に分析する方法として、試験溶液を吸水性樹脂上に濃縮捕集し、マイクロウエーブで乾燥させた後、蛍光X線装置で多成分の重金属を同時に分析するという方法を開発した。これにより、不法投棄事案等が発生したときに、早期に環境影響や投棄物の有害性の判定をすることができるようになった。
2 最終処分場に関する精密調査
安定型、管理型処分場の浸透水・周縁地下水、埋立廃棄物及び場内地中ガス等について、重金属類、VOC、PCB、TOC、化学物質等の濃度を調査し、埋立廃棄物の種類の影響、降雨の影響、安定化の状況等について考察を行った。現在までのところ、一部試料採取時における懸濁物質混入の影響を受けた例を除き、規制基準等を超過する例は認められずおおむね適正な維持管理がなされていることが確認された。