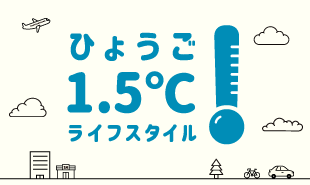第1節 大気環境問題と対策
兵庫県の大気汚染は、昭和30年代からの高度成長期を通じて、エネルギー消費量が急速に増大するとともに、石炭から石油へとエネルギー源が転換されることにより、大気汚染が当初はばいじんを中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させつつ広域化、深刻化していった。
昭和40年代半ばには、兵庫東部地域で光化学スモッグによる被害が発生するようになったため、昭和46年には「光化学スモッグ防止対策暫定要領」を制定し、その対策を開始、さらに、「兵庫県広域大気汚染緊急時対策実施要綱」、「阪神広域大気汚染対策実施要綱」を制定し、大気汚染の防止と緊急時の対策を強化した。
昭和40年代も終わりになると、硫黄酸化物は相次ぐ排出基準の強化により改善の兆しを見せ始めたが、抜本的な改善にはいたらず、昭和49年には「大気汚染防止法」の一部改正により、総量規制が導入され、本県では阪神地域(昭和51年)及び播磨地域(昭和52年)で総量削減計画及び総量規制基準を設定した。これらの規制及び脱硫装置の導入、燃料の低硫黄化等により、本県の硫黄酸化物による汚染は着実に改善された。
一方、窒素酸化物による大気汚染が新たな問題として認識されるようになった。昭和48年には、二酸化窒素の環境基準(昭和53年に改訂)、工場に対する排出基準(以降、順次強化)が定められ、さらに、昭和59年には、「阪神地域窒素酸化物総合対策推進要綱」を策定し、これらに基づき規制指導を行った。
また、モータリゼーションの進行により、昭和40年代から問題となってきた自動車排出ガスによる大気汚染、騒音等の自動車公害であるが、昭和50年度以降排出ガス、騒音について相次ぐ自動車単体規制の強化が行われるとともに、昭和55年には「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制定され、昭和57年に国道43号及び阪神高速道路が沿道整備道路に指定された。
航空機騒音に係る環境基準(昭和48年)、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年)が設定されたのもこの時期である。
昭和50年代には改善の傾向が見られた二酸化窒素濃度は昭和60年代に入ると再び上昇の傾向を見せ始めた。従来の固定発生源の対策に加え、自動車交通量の増大に対応した対策が必要となり、平成4年に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が制定され、阪神地域が特定地域に指定された。平成5年には「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」が策定され固定発生源等の対策を行ってきた。
平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、低濃度であっても長期的暴露によって健康被害が懸念されるベンゼン等の有害大気汚染物質について、環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
平成11年7月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が公布され、環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
また、平成13年6月には、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が公布され、対象物質に粒子状物質が追加されるとともに、阪神地域と播磨地域が窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(対策地域)に指定された。
この法律により、平成14年10月から対策地域内において、車種規制(排出基準を満たさない車両の登録規制)が実施されている。
さらに、県では、環境基準の達成をより確実なものとするため、平成15年10月に「環境の保全と創造に関する条例」を改正し、特別対策地域(阪神東南部2区4市)内での排出基準を満たさない自動車の運行規制を平成16年10月から開始することとした。